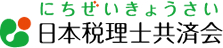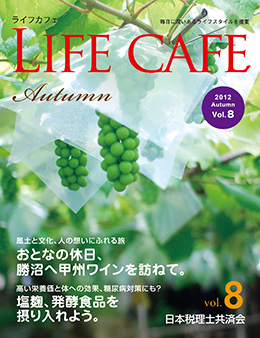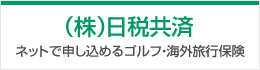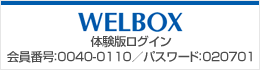HOME > 特別対談企画「税理士相互扶助について語る」


(司会者:高田専務。以下「司会者」)平成23年3月11日に発生した東日本大震災から1年が過ぎました。
本日は日本税理士会連合会・池田隼啓会長と日本税理士共済会・井山要一理事長のお二人に税理士業界における助け合い、日本税理士共済会が担う相互扶助についてお話しを伺いたいと思います。
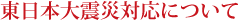
(池田会長)早いものでもう1年が過ぎました。改めて亡くなられた方々のご冥福と、被災された皆様の1日も早い復興をお祈りいたします。
日本税理士会連合会では、私が本部長となって東日本大震災救援対策本部を設置し、会員の安否確認、全国の税理士、税理士関連団体からの義援金の募集と配布、被災会員への支援をはじめ、被災地における所得税・贈与税の確定申告期限の延長等の国等への税制要望、無料税務相談等の納税者への支援を行いました。
私自身も被災地に伺い、会員や住民の皆様の声を聴き、肌でその深刻さを受け止め、人と人との助け合いの大切さを感じて参りました。
(井山理事長)日本税理士共済会においては震災特別会計を設定し、日本税理士会連合会及び被災地の税理士会に義援金を出捐するとともに、被災された加入会員に対しお見舞金の拠出を行い、これまでに約400名の被災加入者に総額1,600万円ほどのお見舞金をお支払いしており、その他にも新規にご加入いただいた方に対して、東北税理士会や東北地域の税理士にご紹介いただいた名産品を贈る等、私たちにできる持続可能な支援を行っています
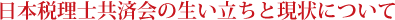
(司会者)日本税理士共済会の発足は自然災害がきっかけだった
そうですね。
(井山理事長)はい、今から約60 年前の1953(昭和28)年、九州・西日本地区で豪雨災害がありまして、私もその当時福岡におりましたので、恐ろしい被害があったのをよく憶えているのですが、このときに当時の日税連会長の松隈秀雄先生が「税理士相互扶助の精神をもって被災会員を救済すべし」との声明を発表し、そのための組織として日本税理士会連合会の中に共済制度調査委員会として誕生し、後に日本税理士会連合会共済会となりました。
(池田会長)1942(昭和17)年に制定された税務代理士法にかわって税理士法が制定されたのが1951(昭和26)年ですから、日本税理士共済会は、税理士制度や日税連の歩みとほぼ時を同じくして生まれたというわけですね。
(井山理事長)日税連が生まれた直後に「相互扶助による福祉」を目的とする組織が立ち上がったことは、まさに先人の叡智に感服するところです。以来60 年近く日本税理士共済会はこの「税理士相互扶助」の精神に基づき税理士自身が組織運営をおこなってきたわけです。
相互扶助の仕組みとして、最初に団体保障制度の募集を開始しました。それと同時に加入者が被災したときの備えとして「見舞金」制度も作りました。これは日本税理士共済会の加入会員で火災、風水害の被害に遭われた方に見舞金を贈るというシンプルなもので、日本税理士共済会の特長です。
見舞金の仕組みこそは助け合いで、損害保険ではありませんから、団体保障の配当金を原資として少しずつ資金を捻出し、助け合い資金を積み立てていった。永年の蓄積が日本税理士共済会にはあるということです。
「見舞金」制度だけではなく、その後様々な共済制度、年金制度が発展しました。
現在では「税理士団体保障」、夫婦一緒に保障の「おしどり保障」の2つの生命共済と「選べる医療保障・マイセレクト」、「所得補償」、「シニアにきちんと医療保険」、「普通年金」、「大型年金」、「個人年金」の3つの年金制度、「ハイパーメディカル(医療補償)」、ゴルファー保険等を扱っています。
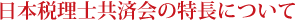
(司会者)業界で働く方の相互扶助のお話をうかがいましたが、加入者の範囲が限定されているのでしょうね。その他に特長、メリットは何でしょうか。
(井山理事長)加入できる方は、税理士、配偶者、事務所職員で業界関係者のみの自由加入です。
保険リスクは保険会社が負担していますが、運営は我々共済会の理事である税理士自らが考えて采配を振るっています。
職員だけでも加入ができる点が特長です。いずれ税理士バッジを付ける方々が今から加入しておいて損はないと思います。団体制度のメリットとして、一般の個人保険に加入するより保険料は割安です。税理士事務所職員の方にも是非とも我々の存在を知っていただきたいですし、税理士事務所の職員福利厚生の一助となるものと思います。
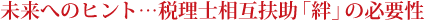
 (池田会長)昨年の大震災の惨状の中にあって、日本人ならではの精神性の高さ、被災地域の方々が助け合う姿を見せられ、税理士業界における相互扶助、助け合いの仕組みができないものかと考えておりました。税理士が安心して仕事をするためには日本税理士共済会のような組織が重要だと思います。
(池田会長)昨年の大震災の惨状の中にあって、日本人ならではの精神性の高さ、被災地域の方々が助け合う姿を見せられ、税理士業界における相互扶助、助け合いの仕組みができないものかと考えておりました。税理士が安心して仕事をするためには日本税理士共済会のような組織が重要だと思います。日本税理士共済会は発足のきっかけが自然災害ですから、当然それへ対応する仕組みが当初からあった。税理士同士の絆、助け合いの仕組みを作っていたということ。
これをもっと大きな輪にしてゆくことが大切であると感じます。
(井山理事長)当時の水害をきっかけとして、税理士の社会的使命を全うするためにも、まず身内が身内を守る仕組みを確立しようということだったと思います。
基本的な助け合いの精神が共済会の基盤であり、相互扶助の精神は共済会を成り立たせるための根本的な原理原則です。その心が今も残っているのが「見舞金」制度ということです。平成7年の阪神淡路大震災、昨年の東日本大震災ともに加入者にお見舞金を贈り、日税連と被災地域の税理士会には義援金を出捐しております。微力ではありますが、間接的な形で税理士業界への貢献ができていると思います。
(池田会長)日本税理士共済会にはさっそく義援金対応をしていただき、感謝しております。
まさに税理士同士の助け合いの精神が今も受け継がれているということを伺い、たいへん心強く思います。
意外とその点が知られていないのではありませんか。
私どもからすれば関連団体であるから理解しているけれども、全国の税理士会員にどれだけ知られているか。もっと積極的にPRをする必要がありますね。
(井山理事長)創立以来これまでの募集活動はダイレクトメールのみで保険会社の営業職員が販売のために税理士事務所を訪問することがありませんでした。「日本税理士共済会は最小限のコストで出来る限りの保障をお届けしたい」、という思いがあるからこそコストをかけないように、また、税理士の貴重な時間を奪わないように、「時間があるときに郵便物を見てください」、という募集方法を先輩方は選択したのだと思います。これからは創立当時の募集活動がそうであったように、税理士の人と人とのご縁による紹介、これも「絆」の活用ですが、人縁を頼りに少し積極的に募集活動をしようと考えています。
(池田会長)成年後見制度、会計参与、登録政治資金監査人、税務支援への対応など、以前にも増して我々税理士に求められる社会的使命はますます多岐にわたり重みを増しているわけですが、税理士が安心して職務を全うするためにも、こうした相互扶助の仕組みを利用して自らの備えを万全にすることを望みたいですね。
(井山理事長)日本税理士共済会は、税理士が税理士のために運営している業界の「絆」であるということを是非ともご理解いただきたいと思います。
先輩が作り上げた歴史ある相互扶助の仕組みは税理士自身で守るという意味でも、最低限の保障は日本税理士共済会の「税理士団体保障」に全員加入してほしいという願いもあります。
支部の互助会制度の後ろ盾として、「税理士団体保障」に支部全員で加入していただいている例もありますし、日本税理士共済会の活用の仕方はそれなりにあるものと思っています。
私たちは先輩税理士が作り上げたこれまでの制度を大切に維持していきますが、新しいものにもチャレンジいたします。ダイレクトメールだけの募集活動だけではなく、今後は積極的に宣伝活動を行えるよう、環境整備のお力添えを池田会長には是非とも賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
(池田会長)日本税理士共済会の大切さは良く理解しております。
今後も出来る限りの協力は惜しまないつもりです。
(司会者)ちょうどお時間がまいりました。本日はありがとうございました。